|
■河川敷へ上り下りする道の不思議
この江戸川サイクリングロードを走ると不思議なことに気が付きます。
江戸川に架かる道路橋や鉄道橋と交差するのに河川敷に下りる場所には、走っている方向へそのまままっすぐ下りたり上がったりできる部分があるかと思うと、Uターンして坂を上がるなり下るなりして、またUターンして先へ走っていくところがあったりします。Uターンするほうはスピードを落として急なハンドルを切らなくてはいけないので、サイクリングロードの進む方向にそのまま上り下りできるようにしてくれればよいのにと思います。
ところが、このサイクリングコースを何度か走ると、堤防と河川敷とで上り下りする道の作りが、大部分の場所で一定の規則で作られていることに気が付きます。
それは次の図のように、
◇ 常に、川の下流方向に向かって坂を下る。
というものです。
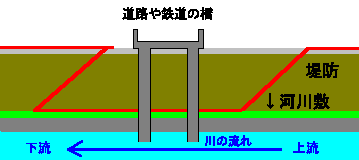 これを書いている時点ではまだ、他の大きな川はあまり走っていないので、他の川でどうなっているかは見ていないのですが、ほかでも同じようになっているのではないかと思います。
これを書いている時点ではまだ、他の大きな川はあまり走っていないので、他の川でどうなっているかは見ていないのですが、ほかでも同じようになっているのではないかと思います。
なぜかというと、江戸川でこうなっている理由を考えてみるとおそらく他でもそうだろうと思えてくるからです。
その理由とは?
こうした構造にしている理由が載ってないか、国道交通省やその河川局、あるいは(社)日本河川協会や(財)河川情報センターといったところのホームページを見てみたのですが、こういう細かいことについての情報は見つかりませんでした。
でも、ちょっと考えると、たぶんこういう理由なのだろうということに思い至ることができます。
もし、川の上流側に向かって下るようになっていたら...。
逆に言うと、川の下流側に向かって上るスロープがあるということになります。
川の堤防は大雨などで増水したときに想定しうる最大の水量でも水があふれないように、余裕を持って設計されているでしょう。
普段見る川はのどかな印象を受けますが、日本の川は普段の状態と増水時の差が非常に大きいといいます。川の中州でキャンプをしていた人が急激に増水した川に取り残されたり、遭難したりしたニュースのときにも、その話は強調されていました。
そして、増水したときの川は単に水位が上がるだけでなく、勢いも非常に強くなっているはずです。その水が流れていく方向に上りのスロープがあれば...
普段なら低い方から高い方へ水が勝手に流れるなんてことはないでしょうけれど、凄まじい勢いでやってくる水なら、高々数メートルの坂くらい駆け上がって堤防を越えて川の外側にあふれ出してしまうでしょう(下図)。
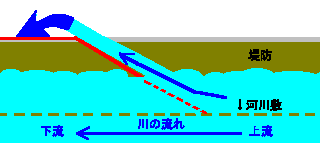 こうした危険を避けるために、常に下流側に向かって下る形にしていると思われます。だから、他の川でもこうなっていることは十分に考えられます。
こうした危険を避けるために、常に下流側に向かって下る形にしていると思われます。だから、他の川でもこうなっていることは十分に考えられます。
なら、先の江戸川東岸の新葛飾橋のところで上流方向に下るという例外が出来ているのは不思議です。
ちゃんとした理由は分かりませんが、昔は下流側に下るように作るという規則がなくて、その頃に作られたのかも知れません。この部分が、まだサイクリングロードや遊歩道として整備されていない状態であることを見ると、そういう気がしてきます。もしそうなら、将来、この区間が整備されるときには下流方向に下る形に作り変えられるのでしょう。
|