資料目録へ|
玄関へ
東西線が止まったときは
新規公開日:1999年7月25日
最終更新日:2025年3月6日
このページは、特に平日の通勤時間帯に東京メトロ東西線が止まっても、他の交通機関は動いている場合に、代替の交通機関-特に鉄道路線-に行徳地区からどうやってアクセスすればいいかを、当サイト作者の体験を元に書いたものです。
ここで、「東西線が止まる」とは動き出す見通しがたたない場合を意味します。
たとえば、電車の脱線のような回復に長時間要する事故だとか、解決の見通しのたたないストのような場合です。
「人身事故」や「信号機故障」、「ポインタ故障」、「車両故障」は、経験的に30分から1時間半程度で運転再開となるので、このような場合は含みません。今は仕事をリタイアしていますが、現役で通勤していた頃、こうしたトラブルで東西線が止まっている場合は、だいたい運転再開まで待つことにしていました。
東西線が止まったときの他路線へのルート
電車の輸送力は自動車やバスとは桁違いなので通勤時間帯に止まった場合、バスやタクシーの乗り場は長蛇の列になり、なかなか乗ることができなくなります。乗れたとしても、もとより道路が混雑している時間ですから、その混雑は一層激しくなり、どの程度時間を要するかはほとんど予測不可能になるでしょう。
こうした場合、一番頼りになるのはやはり自分の脚です。他の路線の駅まで歩いていくのが一番確実です。
他路線とは以下になります。
- 行徳臨海部を通るJR京葉線
- 江戸川区を通る都営新宿線
東西線が止まったときの他路線へのルートマップ
この地図はペイントソフトで描いた概略図です。実際のルート確認は市販の市街地図でお願いします。
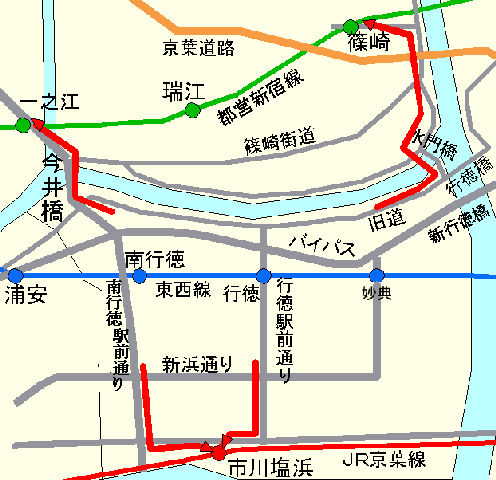
旧江戸川の水門橋(篠崎水閘門)は自動車の通行はできません。
上の地図に示したように、3つのルートが考えられます。
以下に示す距離はいずれも市販の市街図上で道路に沿って、定規を当てて測った長さに縮尺率を掛け算して出したおおよその値です。
1.JR京葉線の市川塩浜駅へ向かうルート
- 行徳駅から市川塩浜駅までは、約2.5kmです。
行徳駅前通りと湾岸道路経由。
- 南行徳駅から市川塩浜駅までは、約2.8kmです。
南行徳駅前通りと湾岸道路経由。
- 妙典駅から市川塩浜駅までは、約3.7kmです。
線路と直角に海側へ向かう道-新浜通り-行徳駅前通り-湾岸道路経由。
このルートの長所は、
というところでしょう。
一方、短所は、
- 行徳駅方面からは、距離的にいっても実際上、市川塩浜駅へ向かうしかないので、混み方が激しくなってしまう。
- 市川塩浜駅は臨海部埋め立て地の産業エリアに位置するため周辺に人家はなく、行徳駅方面も南行徳方面も人家のあるところまで約1kmはある。朝はともかく夜の帰宅時はひと気がない暗い道を歩かなくてはならない。
というところでしょうか。
2.今井橋を渡って都営新宿線の一之江駅へ向かうルート
- 南行徳駅から一之江駅までは、約2.5kmです。
南行徳駅前通り経由。
- 行徳駅から一之江駅までは、約3.7kmです。
市川浦安バイパスと今井橋への大通り経由。
(注-今井橋からの大通りは2014年に、相之川の市川浦安バイパスとの交差点から湾岸道路との交差点までの市川市市道区間が「南行徳駅前通り」と名付けられました。バイパスとの交差点から今井橋までは千葉県県道50号線で特に名称は付いていません。また、それ以前は今井橋通りという通称で呼ばれていました。)
このルートの長所は、
- 幹線道路で行けるので分かりやすい。
- 今井橋、瑞江大橋の上以外はほぼ街中を通る。
というところでしょう。
一方、短所は、
というところでしょう。
3.水門橋(篠崎水閘門)を渡って都営新宿線の篠崎駅へ向かうルート
- 行徳駅から篠崎駅までは、約4.5kmです。
行徳駅前通り-行徳街道(旧道)で行徳橋南詰まで-江戸川放水路堤防上の道を通って水門橋(篠崎水閘門)-江戸川沿いの道で京葉道路の高架をくぐった200mくらい先まで-左へ曲がって篠崎駅まで。
- 妙典駅から篠崎駅までは、約3.4kmです。
寺町通り-行徳街道(旧道)で行徳橋南詰まで-江戸川放水路の堤防上の道を通って水門橋(篠崎水閘門)-江戸川沿いの道で京葉道路の高架をくぐった200mくらい先まで-左へ曲がって篠崎駅まで。
このルートの長所は、
- 行徳街道(旧道)側の行徳橋寄りエリアからは他の駅より比較的近い。
- 都営新宿線篠崎駅は、始発駅の本八幡の次なので、比較的乗りやすい。
というところでしょう。
一方、短所は、
- 水門橋(篠崎水閘門)までは、行徳駅エリアからでもかなりある(行徳駅からで2.8km)。妙典駅からでも直線距離でも約1.3km(行徳街道経由だと約1.7km)ある。
- 水門橋を渡ってから篠崎駅までは直線距離では約1.2kmだが、まっすぐ行ける分かりやすい道がない。
- 行徳橋南詰めから水門橋までの堤防上の道は、人家がなく、夜間はひと気がなくなる。
と、条件的に他のルートより厳しくなります。
1992年3月、東西線が止まった日
(東京メトロになる前の営団地下鉄の頃です)
1980年代以降は大手の電鉄で春闘のストで電車が止まることは、少なくなっていて、当サイト作者も1984年に就職してからストで電車が止まってしまった経験は一度もありませんでした。ですが、この1992年の3月(の何日かまでは、さすがにもう失念しました)だけは例外的に、営団の労使の交渉が長引いたようで、昼近くまでだったと思いますが、営団地下鉄全線がストップしました。
この日の前の晩、寝るときもTVのニュースではまだ未解決だということでしたが、でも朝には解決して電車はいつもどうりに動くだろうと予想し、念のため、目覚ましはいつもより30分は早い6時すぎくらいにセットして眠りにつきました。
で、翌朝、目覚ましで起きて、TVをつけて見ると、なんと、時間切れでストに突入しているではありませんか。あわてて飛び起きて服を着て、ひげを剃ってみづくろいをし、鞄に手帳等々を放り込んで、6時50分くらいに家を出ました。
当時、住んでいたのは南行徳のバイパス側で少し行徳寄りのほうだったで、行徳街道(旧道)のほうへ出て今井橋へ向かいました。今井橋の大通りに出ると、さすがに一之江駅へ向かう人がかなり歩いていました。今井橋、新中川をわたる瑞江大橋をわたって一之江駅までは、少し早足で歩いたので20分ちょっとでした。
ところが一之江駅に着くと、切符の自動販売機まで長蛇の列(注.交通系ICカードの登場は2000年代からで、この頃はまだない)。自動販売機以外切符を買うところなし。そりゃそうです。たとえば、近くに高校や大学があって入試のスケジュールがわかっているとか、そういった場合なら、係員を増員して臨時の切符売り場を設営するでしょうけれど、あるかないか分からない他社のストに備えて、(人件費かかるのに)余分な要員を配置しておくなんてするわけないです。事故で東西線が止まったときなどでも同じようになるのでしょう。
そして、切符が買えるまでまた25分くらいかかりました。だけど、並んでいた人はほとんど東西線方面から来たサラリーマンやOLのようで、みなさん我慢強く順番がくるまで静かに待っていました。
やっと切符が買えてホームに入ると、以外と人が少なかったです。切符を買うのに時間がかかるのが、入場制限をしたのと同じ効果あったためでしょう。新宿線も篠崎部分開通から5年くらい、本八幡開通から2~3年くらいだったと思いますが、そんなに混んでいませんでした。電車が船堀、東大島と進むにつれ人が乗ってきて、それでも普段の東西線並というくらいでした。
(これが1992年当時の状況ですが、現在は沿線人口が増えて、もっと混んでいるのではないかと思います。)
当サイト作者の当時の勤務先最寄り駅が門前仲町だったので、森下駅で降りて清澄通りを南下し、20分ちょっとで会社に着くことができました。もし、もっと都心寄りなら営団が止まっていたので、もう一苦労したところでしょう。
会社で、話を聞くと、行徳駅の妙典側に住んでいる人は、京葉線の市川塩浜駅から来たそうですが、途中の道は市川塩浜駅へ向かう人が延々と連なっていたらしいです。(ふだんから乗降客がそんなに多くない駅ですから券売機も少なくて)切符を買うのにも1時間近くかかったとかで、さらに電車に乗るのも一苦労で、電車はぎゅうぎゅう詰めで超満員(注.当時の京葉線の運転本数はまだそれほど多くない頃)。東京駅手前の越中島や八丁堀では降りることができず、終点の東京駅まで連れて行かれたとういうことでした。
それ以外に東西線が長時間止まったのは、この1992年のスト以降だと、一度、南砂町と東陽町の間の深川の車庫へ行く線路が分かれるあたりで、線路工事でのミスが原因で、朝一の電車が脱線し、地下線なので大型の機械を持ち込めず、復旧までほぼ一日近く止まったということがありました。
でもその日は休日で、しかも当サイト作者は前夜の飲酒のため昼過ぎまで寝ていて、さらに起きてからもダラダラ過ごしたので、東西線が止まっていたことは翌日の朝刊を読むまで知りませんでした。
2000年8月7日、東西線が止まった日
& 葛西から行徳へのルート
(東京メトロになる前の営団地下鉄の頃です)
2000年8月7日(月)、この日の帰宅時間帯、東西線が止まりました。
夜8時前に激しい雷雨があって妙典駅に落雷し、架線が外れてしまったということで、東西線は中野~葛西間の折り返し運転になり、葛西と西船橋の間は結局、終電までストップしたままでした。それで、この日はしょうがなく、葛西から南行徳の自宅まで歩きました。
その頃は残業が多かったですが、都内の会社の最寄り駅に駅に着いたのが、午後9時10分くらい。そのときは妙典で落雷のため、中野~茅場町折り返しと出ていたのですが、ホームへ降りると葛西までは行くとのこと。ずっと以前も、東西線で信号機か何かの故障で、葛西まで運転というので葛西まで行くと、もう復旧していてそのまま西船橋まで運転されたことがありました。今回も同じようになることを期待して、やって来た葛西行きに乗って葛西まで行ってみました。そこまできて、ようやく落雷のダメージがかなり大きなものであることが分かりました(妙典で架線が外れたことが分かったのは翌日、会社でニュース系のサイトを見てからでした。)。都内の駅でそれが分かれば、都営新宿線のほうに回って一之江から歩いて帰ったでしょう。当時、こうしたときの営団の情報伝達はおよそ悪いものでした。
そして葛西へ付くとホームはそれまでに着いた電車から降りた人で一杯で、おまけにこのとき葛西駅のホームはエスカレーター工事で片方の階段は閉鎖中。もともとホームが狭い葛西だから、駅の外へ出ようとしても、人の列は全然前へ進みません。ホームの端まで人が一杯なので、着いた電車を反対ホームへ回送しようにも動かせない状態(だから当然、ダイヤも大混乱のはず)。それでも少しずつ進んで、改札を出るまで15分か20分はかかりました。これでもう午後9時45分はすぎていたでしょうか。
電車の復旧を待つか、歩くかどちらか選ばなくてはいけないけれど、まだ夕食を食べていなかったので駅近くの店で食事し、出てきたのが午後10時半ちょっと前でした。葛西駅へ戻ってみても、西船橋方面は復旧のめどがたたないとアナウンスが繰り返されているばかりでした。
しょうがないので、「葛西からウォーキングでもするかー!」と当時、住んでいた南行徳まで歩くことに決めました。この日、会社を出た頃にはまだ雨が降っていたけど、このときはもうやんでいたので、スーツの上着を手に持って歩けたのは幸いでした(注.まだクールビズやビジネスカジュアルが広がる前で、夏でもスーツ(もちろん夏物)で上着を着るのがふつうだった頃)。
葛西駅を出発したのがちょうど午後10時半頃、まず環七通りをしばらく北上し、葛西橋通りとの交差点で浦安方面へ右折。そのまま、まっすぐ進み、旧江戸川べりに着くまで20分でした(一応、大人の男の足で歩いた時間です-以後も同じ。もっとも女性の方もけっこう速いペースで歩いていました。当サイト作者は食事をしてすぐだったので、脇腹が痛くならないようにややセーブしていましたが)。
旧江戸川を渡る橋は「浦安橋」です(ちなみに通りの名前についている「葛西橋」は荒川のほうの橋)。浦安橋の上は歩いている人はかなりいました。かなりと言っても、休日の繁華街のような人混みではなく、平日の朝の駅へ向かう道よりやや少ない程度だったです。
浦安橋を渡って浦安の駅前に着いたのがちょうど午後11時でした。下の地図は、市販の地図を見ながらマウスで描いたのです(浦安と葛西の間は短めになってしまいました)。葛西駅から浦安橋までは直線距離では、東西線の浦安~南行徳間と同じくらいですが、直線的に結ぶ道が無くて、環七通り-葛西橋通りと三角形の2辺を通ることになるので時間がかかってしまいます。それから、浦安橋から浦安駅も、電車に乗って旧江戸川を渡るとすぐに浦安駅という感じですが、歩くと、思ったより時間がかかります。
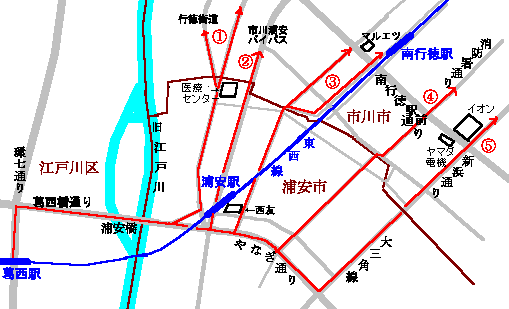
さて、浦安から行徳方面へは目的地によってルートがいくつか別れます。
しかも幹線道路以外の住宅地の中を行く道は、浦安市と行徳(市川市)との間で通り抜けられるところが少ないので分かりにくいです。
昔は田圃や蓮田だった東西線側を区画整理したときに、市川市と浦安市で別々におこなった結果、境界のところで道路がうまくつながっていなくて、ところどころに人と自転車、バイクだけが通れるような抜け道があります(当サイトのこちらのコンテンツをご参照)。
行徳方面へ向かうにはこうした場所を抜けて行かなくてはなりません。
浦安駅のところから、行徳方面への道は概ね上の地図の5つのルートになるでしょう。
- 1.行徳街道(旧道)へのルート
浦安橋を降りたところで左に向かう道を進み、浦安駅の手前で左へ。そのまま進むと、浦安-市川境界の東京ベイ・浦安市川医療センターのところで道が二手に分かれます。左に分かれる方が、昔からの町を通って行徳橋へ向かう行徳街道です。まっすぐ行くほうは古い時代の内匠堀という灌漑用水路の跡が道になったものです。こちらはバイパスの北側百数十メートルを並行して、江戸川放水路近くまで続いています。
- 2.市川浦安バイパスへのルート
浦安駅のところで、市川浦安バイパスのほうへ曲がって行徳方面へ向かうルートです。幹線道路を行くので分かりやすいのが長所。しかし、行徳駅、妙典駅はわりあい近くを通りますが、南行徳エリアでは東西線とはけっこう離れたところを迂回するので、線路に沿って行くより遠回りになるのが短所です。
- 3.南行徳駅方面へ向かうルート
浦安駅そばの西友の横を抜けて東西線をくぐり、南行徳駅近くのマルエツ北側の道に向かうルートです。東西線の線路沿いに、南行徳からさらに、行徳、妙典方面へ向かうにもこのルートが使えます。
浦安・市川の市境はグリーンベルトに開いた抜け道を通ります。
- 4.市川南消防署の通り(カリフォルニア通り)方面へ向かうルート
やなぎ通り(葛西橋通りで浦安市内へ入ってからの通りの名前)の浦安駅入口からさらに先へ進み、道が緩く大きくカーブし終わったところの、ダイエー浦安駅前店がある北栄3丁目の交差点を左へ曲がります。道は浦安・市川市境まで続いています。
この道を進み、市境のグリーンベルトに開いた抜け道を抜けます。そこから右手(南側)約20メートルのところにT字路があって、そこからの道が、東西線と新浜通りの中間を通る市川南消防署の通り(もっと妙典方面に行くと「カリフォルニア通り」の愛称が付いている道)です。
- 5.大三角線~新浜通りへのルート
やなぎ通りを浦安駅入口から約600メートル進んだ交差点で交差する道が大三角線です。ここを左へ曲がると、市境を越えて、新浜通りを行徳方面に向かえます。
さて、2000年8月7日に当サイト作者が浦安駅のところから南行徳方面へ歩いた道は、上の3.の浦安の西友の横を通って南行徳のマルエツ脇に抜けるルートです。やはり浦安から先は歩く人の数もかなり減りましたが、この道を同じように歩いている人はいました。
当時、住んでいた場所の関係で、南行徳駅のほうへは向かわなかったのですが、南行徳公園のそばのセブンイレブンに着いたのが午後11時15分頃ですから、浦安駅前からほぼ15分でした(つまり葛西駅前から45分)。このセブンイレブンと南行徳駅との間もすぐなので、マルエツ付近から南行徳駅前へ向かったとしてもほとんど同じ時間で着いたでしょう。
それで、セブンイレブンで2,3分の間、翌朝の朝食など調達して、家に着いたのが午後11時25分頃ですから、途中どこにも立ち寄らなかったとして葛西から50分余りかかったことになります。
スーツの上着を手に持っていたとはいえ、やはり夏、Yシャツもアンダーシャツも汗でぐっしょりとなっていました。
もし線路沿いにさらに行徳、妙典方面へ向かったとしたら、
- 南行徳~行徳間を歩いた場合、かかる時間は自分の経験で言えば約20分なので、葛西からだと約1時間5分
- 行徳~妙典間は、同じく約15分なので、葛西からだと約1時間20分
ということになります。
南行徳-行徳間に家があるなら、何とか歩こうと行く気にもなるかもしれませんが、妙典だとちょっと遠いですね。やはり、京葉線の市川塩浜駅からということになるでしょうか。
それから、こうしたトラブルのときに東西線が葛西折り返しになるのは、葛西駅に折り返し用の上りと下りの線路をつなぐポインタがあるからです。他にそういう設備があるのは、葛西よりも都心側だと東陽町、西船橋側だと妙典になります。今回は、妙典がアウトだったので、葛西止まりになってしまったのでした。
でも、葛西はホームが狭くて混乱しやすいし、浦安との間は都県境があって、バス路線もろくにないのですから、最低でも浦安駅に折り返し用のポインタを付けて、旧江戸川を渡ったところまで電車で来れるようにしてほしいと思えました。
(2025年3月現在、折り返し設備は変わっていないので、妙典での折り返しが不可で葛西までしか来れなければ、同じように葛西から歩くことになります。)
資料目録へ|
玄関へ
|