アマゾンも楽天も |
 第一貨物 (https://www.daiichi-kamotsu.co.jp/) 塩浜一丁目 |
 福山運送 (https://corp.fukutsu.co.jp/) 塩浜一丁目 |
 JEF物流 (https://www.jfe-logistics.co.jp/) 塩浜一丁目 |
 オリックス不動産 (https://www.orix-logi.jp/) 市川千鳥町ロジスティクスセンター 千鳥町 |
 プロロジス (https://www.prologis.co.jp/) プロロジスパーク市川II 高浜町 |
 西濃運輸 (https://www.seino.co.jp/) 本行徳(住居表示未実施区域) |
 三菱電機ロジスティクス(2024年にMDロジスに社名変更) (https://www.mdlogis.co.jp/) 塩浜三丁目 |
 東陽倉庫 (https://www.toyo-logistics.co.jp/) 塩浜三丁目 |
プロロジスやオリックス不動産が作ったテナント募集型の物流施設、運輸会社、メーカー系の原材料や部材を運ぶための物流会社、他には建築系の部材の物流会社などもありました。
なお、ここに載せたのは一部で、行徳臨海部に存在するすべての物流施設ではありません。
念のため。
■行徳隣接地域では..
では、物流施設は行徳の臨海部にだけ集中しているのか、隣接地域も見てみましょう。

江戸川放水路を渡って、高谷、原木のほうへ行くと、近鉄エクスプレス(https://www.kwe.com/jp/)をはじめとして、いくつかの物流施設があります。
浦安は鉄鋼通り、それと隣接する千鳥、港という町名の地域が工業地帯ですが、「鉄鋼」という文字が町名に入るように金属材料のメーカーが中心です。物流施設もそうしたメーカー関連の輸送を行なうものが主となります。

江戸川区は臨海町にトラックターミナル(https://www.j-m-t.co.jp/terminal/kasai.html)や卸売市場があります。

荒川を渡って江東区に入ると、新砂にプロロジスパーク東京IIをはじめとする施設がいくつかあります。写真のプロロジスの施設は清砂大橋上から写したものですが、東西線の車窓からも見ることができます。
行徳臨海部だけでなく、隣接地域も含め、湾岸の高速道路沿いの地域の多くが物流拠点-主に首都圏の物流のための拠点-となっていることが分かります。
■かつての行徳の物流拠点-祭礼河岸
行徳の郷土史について書かれたいろいろな本を読むと、かつて(江戸時代から明治時代にかけて)の行徳にも江戸へモノを運ぶための物流拠点が存在したことが分かります。
 旧江戸川沿い押切で今は押切排水機場がある場所が、かつて水運が栄えた時代には祭礼河岸と呼ばれた物流拠点でした。「祭礼河岸」という名前は通称で、本来の名前は「行徳河岸」です。
旧江戸川沿い押切で今は押切排水機場がある場所が、かつて水運が栄えた時代には祭礼河岸と呼ばれた物流拠点でした。「祭礼河岸」という名前は通称で、本来の名前は「行徳河岸」です。
 2005年頃から旧道沿いの地域各所に歴史案内板が立てられ始めましたが、押切排水機場の前にも行徳河岸(祭礼河岸)旧跡の案内板があります。
2005年頃から旧道沿いの地域各所に歴史案内板が立てられ始めましたが、押切排水機場の前にも行徳河岸(祭礼河岸)旧跡の案内板があります。
この案内板(それから郷土史の本)によると、今の押切排水機場の場所に河岸が設けられたのは1690年(元禄三年)のことで、それ以前は1631年(寛永八年)ごろまでに設けられた河岸が、別の場所にあったと推定されています。
 その別の場所というのが、同じ押切の稲荷神社やその近くにある光林寺から、今の市川浦安バイパスにかけての区域です。写真は光林寺の前からその区域を見たもので、奥が行徳駅の方向です。
その別の場所というのが、同じ押切の稲荷神社やその近くにある光林寺から、今の市川浦安バイパスにかけての区域です。写真は光林寺の前からその区域を見たもので、奥が行徳駅の方向です。
ここに河岸があったというのを、今の時代のわれわれが聞くと疑問が湧いてきます。江戸川(旧江戸川)に面していないのに、どうやって船を着けることができたのかと。
それは、昔はこの場所が海のそばだったから。行徳は江戸川が運んできた土砂が堆積した州の上にできた町ですが、江戸時代初め頃は州も細長く、今の市川浦安バイパスのあたりはもう海でした。行徳で生産される塩を江戸に運ぶための水路として、江戸時代の初めに今の江東区の小名木川、江戸川区の新川が掘られ、行徳との間の水路(別名 行徳川)が出来上がりました。当初、江戸からその水路を通ってきた船は、今の浦安の当代島にあった舟圦川(現在は緑道になっている)を通って一旦、海に出てから河岸に着いたということです。
江戸時代の初期は戦乱の時代からあまり時間も経っておらず、徳川幕府の支配体制も十分とは言えなかったようで、江戸の防衛上の理由で江戸川の上流との船の行き来が制限されていたということです。それが、幕府が出来て100年近く経つと世の中も安定し、また徳川家康の江戸入府以来、行なわれてきた関東平野を流れる川の流路の大規模な付け替え工事もほぼ完成し、銚子~関宿~行徳~江戸の水運ルートが出来たことも、河岸が江戸川沿いに移された大きな理由でしょう。
 押切の行徳河岸(祭礼河岸)は貨物専用の河岸でした。では、人(旅客)が船から乗り降りした河岸はどこだったかというと、むしろこちらのほうが有名ですが、本行徳四丁目にあった「新河岸」です。ここは、常夜燈がある新河岸跡として知られていましたが、2009年(平成21年)末に常夜灯公園として整備されました。
押切の行徳河岸(祭礼河岸)は貨物専用の河岸でした。では、人(旅客)が船から乗り降りした河岸はどこだったかというと、むしろこちらのほうが有名ですが、本行徳四丁目にあった「新河岸」です。ここは、常夜燈がある新河岸跡として知られていましたが、2009年(平成21年)末に常夜灯公園として整備されました。
行徳河岸(祭礼河岸)に1690年以後の江戸川沿いの河岸と、それ以前の河岸があったのだから、こちらも同様の旧の河岸がありそうです。
 その"旧"河岸があったと推定されるのは本行徳四丁目と接する関ヶ島のバイパス側の区域です。行徳五ヶ町の祭礼のとき、本行徳四丁目から本塩への神輿渡御に使われる、本行徳と関ヶ島の境界の道は神輿みちと呼ばれていますが、その神輿みち沿いにある行徳あけぼの保育園のあたりではないかと言われています。(この写真は2011年5月8日撮影)
その"旧"河岸があったと推定されるのは本行徳四丁目と接する関ヶ島のバイパス側の区域です。行徳五ヶ町の祭礼のとき、本行徳四丁目から本塩への神輿渡御に使われる、本行徳と関ヶ島の境界の道は神輿みちと呼ばれていますが、その神輿みち沿いにある行徳あけぼの保育園のあたりではないかと言われています。(この写真は2011年5月8日撮影)
ちなみに、こちらにあったとされる旅客用の船着場の本来の呼び方は「行徳船津」で、貨物用の「行徳河岸」と区別されていました。言葉の使い方が時間とともにいい加減になるというのは昔からあったようで、江戸川沿いに移されてからは「新河岸」というふうに、「河岸」という言葉が使われています。
行徳河岸(祭礼河岸)に話を戻しましょう。「祭礼河岸」という別名はどこから付いたのでしょうか。「葛飾誌略」には2つの説が載っているということです。
ひとつは弁天祠があったからということ。確かに祠に神様を祀っていれば、祭礼も行なわれるでしょう。
もうひとつは西連というお坊さんが住んでいたからということ。それで、「せいれん」→「さいれい」になっていったという話です。
どちらが本当か、それともどちらも外れなのかはもう確かめるすべがありませんから、郷土史の本にも祭礼河岸という呼び名の由来ついての確かな根拠は書かれていません。
それともう一つ、「祭礼」と付くようになったのは、街道を来た荷駄を積んだ馬の隊列が着いたときの賑やかさが祭りのときのようだったからという話もあります。
■物流拠点としての行徳が持つ利便性
街道を馬が運んできた荷駄とは一体、何でしょうか。行徳は江戸川、利根川の水運が活発になった後はいろいろなモノを一大消費地である江戸に運ぶ中継点でした。水運だけでなく、佐倉、成田や千葉方面への街道も通じていましたから、これら街道でもいろいろなものが運ばれてきたでしょう。そして、江戸時代初期から大きな役割を果たしていたのが、木下(きおろし)街道を運ばれてきた、銚子や利根川下流域からの鮮魚など生鮮食品を江戸に運ぶ中継点としてのものでした。生鮮食品を運んだ道ということから、木下街道は別名「なま道」と呼ばれていたということです。木下街道は行徳に河岸が設置されたのと同じ時期に徳川幕府によって、まさにその目的で作られた道でした。
鮮魚を運ぶと言っても、冷蔵や冷凍の技術もいけすを載せるトラックもない時代です。魚が腐らないように血を抜くとか内臓を取り去るとかをして、さらに笹の葉に挟むという処置を施して運んだのでした。銚子から木下河岸までは船、木下河岸から行徳河岸までは馬に積み、行徳河岸からは再び船で江戸日本橋の河岸へと向かいます。だいたい、丸1日から1日半かかったということです。
さて、木下街道ですが行徳からだと八幡を経由し、利根川に面した今の千葉県印西市の木下に至ります。木下街道と江戸川、利根川、そして行徳と江戸との関係を地図にすると次のようになります。
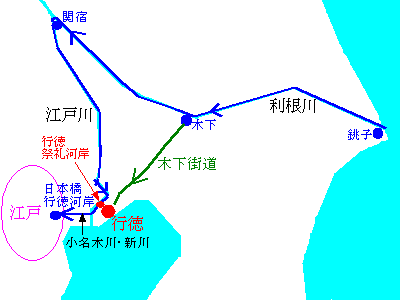
といっても、決して行徳だけが江戸に対する特別な場所だったというわけではないでしょう。江戸の周辺には何本もの街道が通り、街道には宿場がいくつもありました。水運に使う川もまた何本もあって、小さな物流の拠点がいくつもあったでしょう。例えば江戸川沿いだと、流山は米の集散地だったということです。関宿やさらに利根川、渡良瀬川を上った古河は江戸への出入りを監視する要衝でした。行徳もそうしたいろいろな拠点の一つです。
では、今の時代の行徳臨海部に集まった物流施設と、それを取り巻く輸送路を考えて見ましょう。主だったものを地図にするとこのようになります。
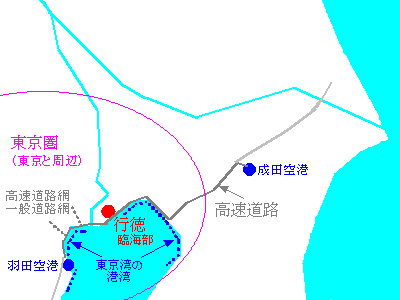
つまりは、物流の拠点として見ると、物を運んでくるにも、消費地に物を運んで行くにも便利な場所だということになります。
行徳や隣接地域が大消費地-東京にごく近いというのは、物流ではやはり有利となるでしょう。モノを運ぶにはコストがかかります。人が徒歩で、あるいは荷車を押したり引いたりして運ぶのも、馬に運ばせるのも駄賃がかかります。距離が長くなるほど駄賃は高くなります。また、人も馬も疲れるので効率が悪くなります。これは、トラックでモノを輸送するようになっても同じです。ガソリン代も運転手の人件費も距離に比例して増えていき、効率が悪くなっていきます。輸送の拠点として利便性が高いというのは、どこへ行くにも便がいい場所、別の言い方をすれば、全体としてのコストを最小に出来るということです。
ただし、これには条件があります。その時代に合った輸送のインフラと、物流の拠点を作るための場所があるということです。江戸時代から明治時代にかけては、川の水運と街道の陸運の中継拠点として栄えた行徳も、輸送手段の主流が鉄道になったら、鉄道が通らなかったことで陸の孤島となり衰退してしまいました。新しい時代の輸送インフラを持つことができなかったからです。でも、さらに時代が進み、埋立地と高速道路が出来たことで再び、物流の拠点としての利便性が活かされる準備が整いました。大消費地である江戸~東京にごく近いという地理的条件は昔と変わっていないので、新しい時代の輸送インフラ、物流施設のインフラを得たことで、今日の状況があるわけです。
といっても、昔と今で違いはあります。かつての祭礼河岸は荷物を積み替える中継点の役割で、今のような物流倉庫として在庫を置いて管理するという機能はありませんでした。冷温保存の技術がない時代には、生鮮食品はとにかく市場へ送り、消費されなければならないので、置いておくことなどできません。では、食品でも食品以外でも保存可能なものはどうかというと、江戸市中に蔵が多くあって、そうしたところに在庫できたので、土地の狭い行徳に置いておく必要はなかったでしょう。今の東京は人口も建物も多くなって、大きな倉庫を作る余裕はないので、したがって、今の行徳臨海部の物流拠点には昔の"蔵"の役割も加わっているのです。
(一方、人の輸送については、徒歩や馬で移動した時代とはスピードが桁違いの乗り物の時代となったので、中継拠点としての役割が復活することにはなりませんでした。東京メトロの東西線は行徳にとっては、東京と結ぶのが主な役割となっています。)
そしてむろん、江戸時代に行徳だけが特別な存在だったわけではないのと同様に、今も行徳臨海部だけが東京圏の物流拠点として特別であるのではありません。東京周辺には物流施設が数多く存在しているでしょう。かつての街道や水運の時代に物流の拠点で、今もまた物流拠点になっているところもあるでしょう。また、今の時代にあった輸送のインフラがないことで、物流とは縁のない地域になっている場所もあるでしょうし、昔は農村と田畑だった場所が工業用地、幹線道路へのアクセスの整備で、新たな物流拠点になったという場所もあるでしょう。
アマゾンや楽天、物流施設開発運営のプロロジスをはじめ、行徳臨海部に物流拠点を設けたそれぞれの企業が、ここに書いたような行徳の歴史を踏まえた上で進出してきたなどということは、まずありえないことです。それぞれの企業が、輸送や立地のためのコスト面で折り合いが付いたことも含めて、その時点で合理的と思える判断をしたからです。あとは、物流センターを建設する土地や、テナントとして入る物流施設にうまい具合に空きがあったからで、これは偶然の要素というべきでしょう。
行徳臨海部を含め、湾岸の高速道路沿いの地域に何かアドバンテージがあるとすれば、やはり成田空港と羽田空港のどちらにもアクセスがよいことが挙げられます。ネット通販の最大手2社が、日本国内の物流施設第一号を行徳に設けるという判断に至ったのは、案外、このアドバンテージが効いたのかもしれません。
■歴史はつながっている
それぞれの企業が合理的と思える判断をした結果、行徳に物流施設を設けることになったのは、東京圏という大消費地に対する物流拠点の役割を果たせる利便性の高い地域だからというのは、間違いのないところでしょう。過去の時代に物流の拠点だったところは、新しい時代のインフラを得ることができれば、同じ役割を果たすことが出来るのです。
アマゾンについてのニュースで2010年のことですが、首都圏の新しい物流拠点を埼玉県の川越に設けたというのがありました。川越というと今は小江戸・川越として観光地になっていますが、かつては新河岸川を通じて江戸にモノを運んだ物流の拠点でした。アマゾンが進出した場所は、小江戸のほうの旧市街ではなく、川越市域の中で関越自動車道へのアクセスがよい工業団地のようです。でも、偶然とはいえ、ネット通販という新しい時代の企業が進出したみたら、そこがかつて物流で栄えた土地というのは面白いものです。
歴史の教科書では、××時代という区分は、縄文時代や弥生時代だと文明の姿かたちで分け、時代が進めば国の統治機能の入れ替わりで平安時代とか江戸時代とかの分け方をしています。そして、時代区分で章を分け、年表のような図表でも時代の区分に線を引いて色分けしてあったりします。小学校の頃からこうしたものを繰り返し見てくると、どうも時代の区分が変わるところで、社会全体がリセットされたかのような錯覚をしてしまいます。でも、こうして地域の歴史を考えて見ても、時代区分が変わったからと言って、地域の姿かたちやそこに住んでいる人間の生活が、がらりと変わることはないと分かります。前の時代からの歴史はそのまま続き、実際の変化はゆっくりと進んで行くのでしょう。明治時代に日本に鉄道が作られるようになったと言っても、明治維新のときに急に鉄道網が出来たわけではなく、社会に大きな変化を起こすのは数十年を要しました。行徳が鉄道が通らずに衰退したのも、明治時代になってすぐというわけではありませんでした。
そして、また時代が進み、埋立地と高速道路が出来て、過去の時代にあった物流拠点としての役割が引き継がれているのです。
 祭礼河岸跡、今の押切排水機場を後ろ側から見たところです。後ろは公園になっていて、公園を出たところが行徳街道と行徳駅前通りとの丁字路です。
祭礼河岸跡、今の押切排水機場を後ろ側から見たところです。後ろは公園になっていて、公園を出たところが行徳街道と行徳駅前通りとの丁字路です。
 行徳駅前通りは祭礼河岸のそばから始まり、ほとんど一直線に海のほうへと向かっていきます。
行徳駅前通りは祭礼河岸のそばから始まり、ほとんど一直線に海のほうへと向かっていきます。
(写真は押切で。行徳駅方向を見たところ。)
そして、行き着くところはというと...
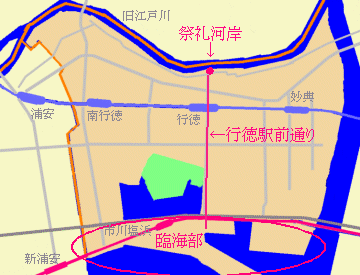 今の時代の物流施設が集まる臨海部です。
今の時代の物流施設が集まる臨海部です。
つまり、行徳駅前通りは歴史の過去と現在をつなぐ道になっているわけです。
行徳の昔は水田だった地域を区画整理したときに、そんなことを意図して道路を引いたわけはありません。あくまでも、偶然の結果であり、後付けの解釈です。
でも、偶然とはいえ、一本の道がこんなふうに通っているというのは不思議なものです。
□参考文献
- 「行徳物語」宮崎長蔵・綿貫喜郎 共著、青山書店
- 「行徳郷土史事典」鈴木和明 著、文芸社
- 「明解 行徳の歴史大事典」鈴木和明 著、文芸社
- 「行徳歴史街道」鈴木和明 著、文芸社
- 「行徳歴史街道2 群像-歴史の主役と脇役」鈴木和明 著、文芸社
- 「行徳歴史街道3 勃興-行徳塩浜の栄枯盛衰」鈴木和明 著、文芸社

 行徳野鳥観察舎の2階や3階から野鳥の楽園の干潟越しに、市川塩浜駅と周辺の建物を見ることができます。その中にいつの頃か、巨大な倉庫らしき建物ができました。
行徳野鳥観察舎の2階や3階から野鳥の楽園の干潟越しに、市川塩浜駅と周辺の建物を見ることができます。その中にいつの頃か、巨大な倉庫らしき建物ができました。 カメラのズームレンズで拡大すると、建物に見覚えがあるロゴ。
カメラのズームレンズで拡大すると、建物に見覚えがあるロゴ。 調べてみると、塩浜二丁目の市川塩浜駅前にあるこの建物はやはり物流センターで、「アマゾン市川フルフィルメントセンター」という名称でした。
調べてみると、塩浜二丁目の市川塩浜駅前にあるこの建物はやはり物流センターで、「アマゾン市川フルフィルメントセンター」という名称でした。 では、日本国内勢はどうでしょうか。国内で大手というと楽天市場を運営する楽天(
では、日本国内勢はどうでしょうか。国内で大手というと楽天市場を運営する楽天( ネット通販はアマゾンと楽天という大手の有名どころ2社が目立ちますが、それ以外にはないのでしょうか。いや、こういう会社がありました。
ネット通販はアマゾンと楽天という大手の有名どころ2社が目立ちますが、それ以外にはないのでしょうか。いや、こういう会社がありました。